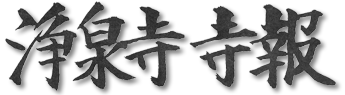
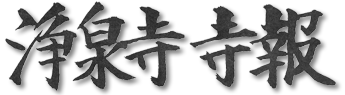 |
◆平成15年1月15日号 |
| ●ともなるいのちに帰る いのちの誕生 住 職 赤羽根 證 信 |
| 帰命無量寿如来 南無不可思議光 あけまして、おめでとうございます。ご門徒の皆様とともに、すばらしい一年になりますことを念じ、更なる精進をお誓い申し上げます。何卒よろしくお願い申し上げます。 一月一日朝、久しぶりに東北別院(仙台)の修正会に出席して参りました。 仙台市内の、ご法中(住職)十名以上が参加、ご門徒の方々も大勢ご参詣に見えられて、午前八時一同で正信偈を唱和、相良晴美東北別院輪番の年頭のあいさつののち庫裡にて新年の会食をいただき、帰山いたしました。 表題に示した言葉は宗祖親鸞聖人作、正信念仏偈の最初の二句であります。 無量寿如来に帰命し、不可思議光に南無したてまつる、と読ませていただいております(つきることのないいのちを信じます。はてることのない光に私をまかせます)。宗祖が九十年の生涯をかけて求めて来た、念仏者としてのあり様を表した言葉であります。 毎年の暮れにその一年をふり返って漢字一文字に表す恒例の京都清水寺管主さん、昨年は〝帰〟でありました。私は重く受けとめて行かねばならないことだと感じた次第であります。 「帰命」いのちに帰る、一人ひとりの人生には数知れぬ喜びと悲しみ、苦しみがあり出遇いがあって今があるのです。 第二次世界大戦以前は自然の脅威から如何にして人間の居住空間を護るか、そして近代ヨーロッパの産業改命の主題は如何にして人間が自然を克服するかという考えの中でその歩みが進められて来たことです。しかし今、「自然を人間から護る」ということが私達現代社会の命題となっている様に思います。その課題を宗祖親鸞聖人に問い耳を澄ませて聞こうと思うと八十六歳の宗祖は 「自然というは、「自」は、おのずからという、行者のはからいにあらず、しからしむということばなり「然」というは、しからしむということば、行者のはからいにあらず。」と記されており、「おのずからしからしむ」、その合意として「行者のはからいにあらず」ということが強調され、さらにそれを「如来のちかいにてあるがゆえに」と言い切っておられます。 自然である如来のちかいは、あらゆるものに〝いのち〟を与え、すべてのものが、ともなる存在として認め合い、死への生でない「願生」という新しい〝いのち〟に帰する生活が、求められて行くのではないでしょうか。合掌 |
| ●比叡のひかり 責任役員 赤 間 栄 夫 |
| 明けましておめでとうございます。門信徒の皆様にはさわやかな新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。 今年は羊年ですので羊について触れてみたいと思います。 広辞苑によりますと羊「ひつじ」のひは(ひげ)つは(つの)じは(うし)の意味で偶蹄目の家畜。毛は灰白色で柔らかくて巻き縮む。角はないものもある。性質は臆病で常に群棲・毛は毛織物の原料。肉は食用・脂・皮も用途が多い・世界各地で飼育されている・ことにオーストラリア・アフリカ・アメリカ南北などで多数飼われている。メリノ種をはじめ品種が多い。緬羊(めんよう) 未「ひつじ」十二支の第八・南から西へ三十度の方角・昔の時刻の名。今の午後二時頃・またおよそ午後一時から三時の間の時刻・陰暦六月の称である。 一乗止観院 親鸞聖人は比叡山に登られ、恵信僧都の教学を常行堂の堂僧として二十年間修行されております。比叡山と対照的に考えられておりますのが高野山です。 高野山は弘法大師(空海)が功成り名を遂げて魂の憩いの場を求められたところであり、今でも信仰の山として多くの人々に親しまれております。 比叡山は伝教大師(最澄)が「人間はいかに生きるべきか」を求めて、十九歳の若さで比叡山に登られ、小さなお堂(一乗止観院)を建てられその中に自分で刻まれたお薬師さんの像を祀られ、灯りをともして 明らけく後の仏のみ代までも 光り伝えよ法のともしび と詠まれました。 延暦という年号 比叡山延暦寺と云われておりますが、桓武天皇の勅願によって延暦という年号が初めてお寺の名前につけられたものです。 延暦とは昔から正法五百年と言い、お釈迦様の教えは五百年は正しく伝えられそのあとは像法千年、お釈迦様の教えは形だけが残る。そして末法の破滅の世界がやってくるというように、正像末の三次が説かれております。 この仏教で説いている仏暦の先延べ、すなわち延ばすという意味で延暦という年号がつけられ、お釈迦様の正しい教えが千年伝えられる。そのような願いが込められて延暦寺とお寺の名がつけられたものと思います。 比叡山には延暦寺というお寺はなく、根本中堂を中心にしてたくさんのお堂がありますが、その総称を延暦寺と言います。 比叡山の特徴とは論・湿・寒・貧とよく言われておりますが、論とは法華教についての論議が盛んに行われている。湿とは湖がある関係で湿気が多い。寒とは読んで字のごとく大変寒いところである。貧とは今でも商売上手ではないので大変貧乏である。 またこのほかにも三大地獄といわれる非常に厳しい修業がありましてその第一が回峰地獄であり、第二が掃除地獄そして第三が看経地獄であります。したがって比叡山は高野山とは違って修行が大変厳しいところですので、修行の山と言われております。 不滅のともしび 比叡山は織田信長の焼き打ちに遇いましたが、伝教大師のともされた灯が幸いにも山形県の立石寺(山寺)に移されておりましたので、三代将軍家光によって根本中堂が再建されますと、立石寺よりふたたび根本中堂に伝教大師の灯されたともしびが移され今でも明々とともっております。 ひともとの比叡の灯り時空(とき)を越え ともり続けよ消ゆることなく 赤間有涯・詠む |
| 平成十四年度の聞法会が十月二十六日仙台市泉区実沢の佛光山西照寺で行なわれた。浄泉寺からは十二名古川の成願寺からは九名計二十一名で参加した。開会宣言、真宗宗歌、勤行、会長挨拶と次第に沿って進められた。 法話は午前と午後行なわれた。 午前の部は会場となった西照寺の住職である星祐盛師の「我を見つめて」だった。師のお話で印象に残った事。古い荷物を片付けていたら十九歳の時の日記が出てきた。時は昭和十九年の戦時下での事だった。志願した海軍での体罰、通信区で行なった戦車を爆破させる訓練、敗戦後軍の倉庫から缶詰を盗んだ事等日記に基づいて実体験を話して下さった。それらの経験を通して自分という人間は「環境が変るととんでもない事をする」「自分が反省する時は自分の都合のよい方にもっていく」という事を聞き私にも当てはまると思った。 昼食は西照寺の役員さんが用意した季節感あふれるお弁当に舌鼓を打った。その後秋の花咲く寺の庭を散策して過ごした。 午後の法話が始まった。テーマは「葬式仏教の歴史」。お話は副住職の星研良師。師のお話で興味深かった事。親鸞は十九年比叡山で修行したが煩悩を消す事ができなかったため山を降りたが、もう一つ理由があった。それは親鸞は堂衆だったという事である。当時比叡山の修行僧は三つの階級に分かれていた。一つは食事の用意や労働を行なう行人。一つは事務や雑役を行なう堂衆。一つは学問し仏教を研究する学匠である。当時の厳しい階級制度の中にあっていかに親鸞が優れた人物でも、どうにもならない厚い壁を破る事ができなかった。それが失望から絶望へと変わり山を降りたのだと師は言いたかったのではないか。親鸞の哀しさや並々ならぬ意志の強さを思った。 法話の後質疑応答、恩徳讃斉唱、閉会のことばで一日の行事が終了した。 |
| 十一月二十三日、浄泉寺恒例の報恩講が、いつもの通り晴天に恵まれて実施されました。 伝統の行事が世代が若くなり例年の様なスケジュールで可能かと心配する方もあり、担当の地域が、新橋、東川原町地区とあって新しいメンバーによる当番でお世話役もとりまとめが大変だった様です。しかし参詣も多く鬼首と古川は貸切バスにてのお詣りで本堂はほぼ満堂に近い人でいっぱいでした。内陣の荘厳も、お花、お供物も立派に飾られ来山した法中の方々も当山の報恩講の充実に讃意を送られていました。 ご法話は二年目を迎えた村田願勝寺住職信楽秀道師は「釋親鸞と名告る」との講題でお話をいただきました。はじめて参詣した方は講の内容のすばらしさに感銘を受けましたと感想をのべておられました。準備し迎える側の役員さん方は、あたり前のことの様に振舞っておられましたが、無事行事が進むということは難しいことなのです。それにつけても役員の皆さんスタッフの皆さんに心より感謝申し上げます。 合掌 |
| 三年毎に本山(京都東本願寺)に参詣しましょう、と呼びかけて十回目ほどになります。 詳細は未定ですが山陰、山陽方面で六月の中、下旬にしようと考えています。いつも二泊三日と定めていますので帰りは飛行機になると思います。 本山に参詣することの大切さは参って見てはじめて知ることの出来る尊いものです。どうぞお誘い合ってご参加ください。すばらしい旅にしたいと思っています。 |
| 二十八万四千二百九十六枚、明治二十八年に再建された本山(東本願寺)のご影堂、阿弥陀堂に葺かれている屋根瓦の数です。これは単に数が多いのを誇るものではありません。この瓦、一枚一枚にはご門徒のみなさんの本山両堂再建に賭けた願いが込められているのです。 先達たちによって受け継がれて来た本山、私達はその本山への願いをのちの世に伝えて行くことが出来るのでしょうか。今百有余年の歳月を経て「私」が問われようとしています。 来るべき宗祖七百五十回忌のご修復に向けて、瓦懇志を募っております。何卒ご協力の程、お願い申し上げます。 真宗大谷派 本山 なお、申込み等、くわしくは住職に問い合せ下さい。 |
| コラム●丸かじり出来る豊かさ |
| お正月いいもんだ。 雪のようなママ喰って、 木っ葉のようなドド喰って、 油のような酒のんで・・ と歌った頃の思い出はなつかしい。年末になるのを一日千秋の思いで待ち、都会からあたたかい母のふところに帰郷したあの時の、みそ汁の味。 昨年発生した、牛乳、牛肉、鶏肉、カキ等、一連の食に対する疑念は私達の中に巣くっている飽食で傲慢な生活のはてにおとずれた警鐘ではなかっただろうか。 コンビニ弁当や外食産業が花ざかり、一分も待てなくなったカップラーメン族に、畑の土の匂いのする曲ったきゅうりを丸かじり出来る豊かさを味わせたいと願うのは、ノスタルジックな老人が故なのだろうか。 |
| あ と が き |
| 年も明けて、いつもの生活がはじまった。まっ先に処理せねばならないのが、年末年始のゴミの山だろう。自分の愛車はきれいにして、ゴミはポイ捨てではたまったもんじゃない。寺のゴミ置場もそうだ。寺報や会報に毎度掲載しているのだが、ご覧になれない外部の方なのか、仏様に手を合わせ何を思うのだろう。 一、造花は、絶対にあげない 一、お供物は、お参りがすんだら必ず持ち帰る 一、茶わん、カン類など燃えない。ゴミは必ず持ち帰る 一、ゴミ置場には、紙、樹木、生花以外は捨てない このままじゃ、ペナルティでも作らねばならないのかと残念に思う文明国人間と自称する我々が公共の場で見せる諸行。 おのおの方、約束は守ろうではないか。ご先祖様が見てござる。言ってござるよ。 |
| 会報のトップへもどる |