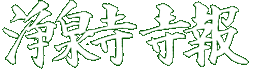
◆平成16年1月15日(第9号)
発行者 浄泉寺住職 赤羽根 證信
- 宗祖親鸞聖人七百五十回ご遠忌 いよいよの時を迎えて
- 宗祖750回御遠忌法要と真宗本廟両堂の修復
- 仙台教区教化センターと東北別院整備事業計画
- 仙台組推進協主催 聞法会に参加して
- 東北別院報恩講参詣と小野川温泉への旅
- 本山瓦懇志のお願い
- 今年上期のスケジュール
- 年回表(平成15年)
- 「献杯」と「いただきます」
- 会報一覧
宗祖親鸞聖人750回ご遠忌 いよいよの時を迎えて
浄泉寺住職 赤羽根 證信
ふかき み法りに あいまつる みの幸 なにに たとうべき ひたすら道を ききひらき まことのみむね いただかん (真宗宗歌)
2004年(平成16年)を迎え、ご門徒の皆様とともに有意義な1年になりますことを念じますとともに、一層の精進をいたして参りたいとの思いを新たにしております。何卒よろしくお願い申し上げます。
昨年11月28日、宗祖親鸞聖人の報恩講ご満座参詣と翌29日のご真影動座式に参詣すべく上山(京都東本願寺)いたしました。
省みれば昭和36年4月、宗祖親鸞聖人700ご遠忌の折、1ヶ月にわたり、本山での奉仕から40年あまりの時を経て、この度750回ご遠忌に向けての記念事業(両堂修復工事)のため、ご影堂での報恩講は約10年間は出来なくなり、私にとっては生涯最後の機会になることだろうとの思いと、ご真影(親鸞聖人座像)をご影堂からとなりの阿弥陀堂への移転のための動座式、このことは迫害や火災などによる緊急避難的なことをのぞけば、宗門はじまって以来の歴史的な仏事に参詣出来た感動的なことでございました。
いよいよ今年からスタートする記念事業は、本山はもとより、私達宗門人にとって「生涯に一度のお手つぎ」であろうかと思います。明治の先達が、維新という近代革命時代の潮流の中で、焼失した東本願寺の再建を果たしたという、本願念仏の存亡をかけて引き継いで来た仏祖の願いを、建物の大きさや立派さのみを固持するのではなく、そこに集う門信徒の聞法の道場として、次の世代にしっかりと伝えるべき使命をも、私達が果たさねばならない大切なことと思っております。
また、これまでも実施して参りました教化活動を再構築する形で、推進員教習、門徒会研修、公開講座、しんらん教室などの一層の充実を計って参りたいと考えております。
昨年の浄泉寺報恩講も、皆様のお陰で立派に勤めさせていただきました。来山した法中の方々も、その内容の充実ぶりに讃意を表しており、ご法話の中でもこの不透明な世にあって念仏者として自在なるいのちを生きるすべを申されました。
本堂建設から早10年、決して平穏でない時代を、念仏者としてひたすら道を聞信して、ご門徒皆様と共に、まことのみ宗を日暮として行きたいと思っております。
合掌
宗祖750回御遠忌法要と真宗本廟両堂の修復
責任役員 赤間 栄夫
ご門徒皆々様には健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
今年は「さる」年です。「申」とは、十二支の第九・西から南へ30度の方角・昔の時刻の名で今の午後4時ごろ、また、およそ午後4時から午後5時のあいだの時刻をいうと広辞苑にあります。
私達真宗大谷派の教団通信には、宗門は2011(平成23)年に宗祖親鸞聖人750回御遠忌を迎えるにあたって特別記念事業として明治の再建以来百年を経た真宗本廟両堂等の修理という歴史的事業に取り組んでゆくことを報じております。
先ず御遠忌を厳修する前年の2010(平成22)年までの期間を御影堂修復工事の第1期工事とし、御遠忌法要の厳修後に行われる阿弥陀堂及び御影堂門の修復工事を第2期工事として取り組む予定です。
現在の両堂は1864(元治元)年の蛤御門の変による焼失の後、明治期における先達の総力を結集し1895(明治28)年に再建されたもので、それから100年の歳月を経て凍害などによる屋根瓦の破損はほぼ全体に及び、その木部においても将来に憂いを残す状態であり明治の再建時の幾多の人々の願いと苦難に思いをいたし、あらためて宗祖が担われた課題を明らかにし信心の生活の回復運動として、宗門挙げて取り組んでほしいとのことです。
- ●懇志について
- 御遠忌・御修復懇志金御依頼願全国総御依頼額・・・198億円
全国各年度御依頼額・・・22億円
仙台教区御依頼額・・・26,856万円
仙台教区各年度御依頼額・・・2,984万円 - ○募財期間について
- 2003年7月1日(2003年度)より2012年6月30日(2011年度)までの9年間
仙台教区教化センターと東北別院整備事業計画
老朽化のすすんだ東北別院本堂・庫裏・職員役宅の再建問題は仙台教区における長年の懸案であり、もう猶予できない時期です。したがってこの度の整備事業は、各種研修会や教学研究所の活動など、教区の教化事業や別院の諸行事、その他の活動に不便をきたしていた諸施設を、教区の経済的な体力を考慮しながら、利用できるものは再利用していく中で、使い易い施設に変えてゆくと同時にそのような一連の作業を通して、教区の教化事業のあり方や東北別院のあるべき姿について問い直し、理解を深めていこうということも併せもっております。
なぜこのような宗祖750回御遠忌・真宗本廟両堂修復の事業に関する募財が始まろうとしているこの時期にという疑問もあるかと思いますが、この問題が教区の課題になってからすでに20年余の歳月を経過しており、本山の募財の済む9年後まで放置しておける状態ではありません。
- ●募財の懇志について
- 教区費御依頼額・・・14,619,000円
教化センター・東北別院整備費・・・79,200,000円
2003年度〜2004年度
東北別院維持費御依頼額・・・1,452,700円
わが国には一年の計は元旦にありという諺があります。年頭に当り謹んで概略をお知らせいたします。何卒深いご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
彼岸会に供えし花か奥津城 に 素枯れたるまま年かわりたり
赤間有涯 詠む
仙台組推進協主催 聞法会に参加して
坊守
平成15年度仙台組聞法会が、去る10月25日仙台市泉区浄満寺様で行なわれました。
浄泉寺と古川成願寺のご門徒さん合計22名、バスで一緒に参りました。はじめて浄満寺様にお伺いしたのは20年ほど前にさかのぼりますので、周辺の環境が大きく変化して戸惑いを感じました。
聞法会には、昨年に引き続き参加いたしましたが、推進協のスタッフの方々や浄満寺様の役員の方々が一生懸命お世話をしている様子に申し訳ないと思いました。
聞法会は、開会宣言、真宗宗歌(エレクトーン伴奏・浄満寺坊守)、勤行(正信偈同朋奉讃)、会長あいさつ、輪番あいさつがあり、午前の法話は浄満寺ご住職久保田毅師がお話し下さいました。ご住職は、仙南組妙頓寺の出身で数年前まで銀行マンとしてお勤めになられていたそうですが、突然浄満寺住職として入寺されました。本人はもともとお寺の出身ですが、奥様はサラリーマンの生活から全く別世界である寺の坊主としての今日が如何に大変であったかと感じた次第です。ご法話の中で、ご住職さんは病気(リンパ腺ガン)になられてから、「生きて行くことの中で、何によって生き、生かされて行くか」を実に淡々とお話しなされました。素晴らしいお話しをお聞きし、身の引き締まる思いでした。
昼食は、浄満寺のご門徒の皆さんのお世話でお弁当をいただき、寺の裏山の整備された墓地や高台から見渡す泉区の都会化する様子をまぶしく見て過ごし、午後の法話は、浄満寺の副住職さんが若々しい中に、今日のために懸命に精進された様子がうかがえてうれしく感じました。浄泉寺でいつか会場になるだろうと思い、坊守さんの姿を探して、いろいろとお話をさせていただき大変勉強になりました。教えに会うということは人に会うということだと思いを新たにいたしました。
寺にもどり参加した方々とお茶をいただき11月23日行う報恩講のことなど話し合い、充実した一日を過ごさせていただきました。
東北別院報恩講参詣と小野川温泉への旅
住職
恒例になった一泊研修を、今回は東北別院報恩講に参詣することにして、10月17日朝8時30分、七日町佐藤呉服店前を出発、参加者22名、仙台市小田原の東本願寺東北別院へ。
10時からのご満座勤行はさすが朗々とひびき、ご法話は秋田本荘市善應寺住職、加納浩師、「生命感覚の回復」の講題で「いのちが一番大切だと思っていたころ生きるのが苦しかった。いのちより大切なものがあると知った日、生きているのがうれしかった」(星野富弘)この言葉が忘れられないと情熱的に問いかけていました。
昼食の後、山形県小野川温泉に向かった。出発前「とてもいいところですよ」との話を杖に、あちらを探しこちらにたずねして5時到着。何か出そうな雰囲気の部屋に案内されました。
一泊でもいつもの顔ぶれ、すぐにうちとけ、皆上機嫌。懇親会は大いに盛り上がりました。
翌日、山形市の篠仏光堂、篠塚社長さんの案内で、紅葉がはじまった名所を廻り、山形市内ではつけもの寿しに舌鼓をうち、つけものなどを土産に求めて、村木沢にある等榮寺に参詣、高橋好善住職夫妻のあたたかい接待を受け、日程最後の七右エ門窯で自作の焼き物作りに腕を振るいました。
参加者の顔は、土を手にしながら戸惑いや期待感などさまざま、その出来栄えを12月13日の集まりでの作品展を楽しみに帰路に着きました。
本山瓦懇志のお願い
28万4296枚、明治28年に再建された本山(東本願寺)のご影堂、阿弥陀堂に葺かれている屋根瓦の数です。これは単に数が多いのを誇るものではありません。この瓦、一枚一枚にはご門徒のみなさんの本山両堂再建に賭けた願いが込められているのです。先達たちによって受け継がれて来た本山、私達はその本山への願いをのちの世に伝えて行くことが出来るのでしょうか。
今百有余年の歳月を経て「私」が問われようとしています。
来るべき宗祖750回忌のご修復に向けて、瓦懇志を募っております。何卒ご協力の程、お願い申し上げます。
合掌
真宗大谷派 本山
なお、申込み等、くわしくは住職に問い合せ下さい。
今年上期のスケジュール
| 1月16日 | 修正会・・・10時 成願寺修正会・・・3時 |
| 2月15日 | 涅槃会・・・10時 |
| 3月17日〜23日 | 春彼岸会 |
| 4月1日〜5日 | 春の法要 於:本山 |
| 5月8日(土)午後2時 | 公開講座 於:仙台青年文化センター |
| 6月14日〜18日 | 門徒会上山研修 |
| 6月27日 | 護寺会総会 |
| 推進員前期教習(3月予定) | |
| 推進員後期教習(6月予定) | |
年回表(平成15年)
| 一周忌 | 平成15年 | 三回忌 | 平成14年 | 七回忌 | 平成10年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十三回忌 | 平成4年 | 十七回忌 | 昭和63年 | 二十三回忌 | 昭和57年 |
| 二十七回忌 | 昭和53年 | 三十三回忌 | 昭和47年 | 三十七回忌 | 昭和43年 |
| 五十回忌 | 昭和30年 | 百回忌 | 明治39年 |
「献杯」と「いただきます」
近頃、法事の供養膳の席で「献杯」という行為を見かけます。
そこで献杯を広辞苑では「敬意を表して杯を人にさすこと」とあります。仏事で行われている献杯は、亡き人に捧げるという意味になるのでしょうか、浄土真宗では献杯という行為はいたしません。
食べ物をいただく時は「いただきます」と合掌してから食します。丁寧には「食前のことば」「食後のことば」を唱和します。
【食前のことば】 み光のもと、われ今、幸いに この清き食をうく いただきます
【食後のことば】 われ今、この浄き食を終わりて 心ゆたかに、力身にみつ ごちそうさま
童話作家の、うの正一さんは幼少期におじいさんから「たべものさまには仏さまがござる、おがんで食べなされ」とよく言われたそうです。正一さんは、ある時、学校の先生に「ご飯の中に本当に仏さまがいるのか」とたずねたところ、「ご飯の中には、タンパク質、含水炭素、脂肪と水分、その他のものは入っていません」と先生は答えました。科学的に分析すれば先生の答えのとおりでしょう。
私たちが食する物は、肉であれ魚であれ、野菜、果物すべて命があるものばかりです。それらの命をいただいて自分の命を保持している。命あるものをいただいているという慚愧と、生かされているという自然の恵みへの感謝の気持ちを抱かざるを得ません。つまり、食べ物は仏さまのいのちをいただくための大きな縁となって働いているわけです。
この様に考えてきますと、法事での杯を献ずるという性格のものではなく、食べ物や飲み物を通して仏さまの命をいただくという、私への問い返しでもあるのです。
真宗会館 広報紙より
宝池山浄泉寺 宮城県玉造郡岩出山町字浦小路113