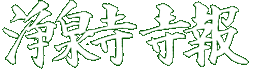
◆平成 18 年 2 月 15 日(第 11 号)
発行者 浄泉寺住職 赤羽根 證信
念佛法難八百年を縁として
浄泉寺住職 赤羽根 證信
2006 年(平成 18 年)を迎え、ご門徒の皆様とともに、意義ある年になりますよう、心から念じる次第であります。
今年いただいた年賀状のメッセージを紹介いたします。
『今年は吉水教団が法難に遇って 800 年になります。 4 名が死罪、 8 名が遠流、宗祖は越後の国府に流罪となりました。しかし、皮肉にもその越後で、その日を生きることに精一杯の人々との出遭いの中で、大地に立つ念佛者親鸞が誕生したといえます。それはまた浄土真宗の原点であり、宗門の嚆矢でもあります。
法難の意味を改めて問い直し、宗門の原点を確め直す「念佛法難八百年法要」が、縁あるところで勤められんことを提案したいと思います。』
あらためて、頷かされました。私達にとって真実の教えに出遭い、その思いを日常の生活者として行ける身でありたいと願っております。
800 年前、宗祖親鸞聖人は 35 歳、それより以前、遡ること聖人九歳のおりに出家されて、天台宗の僧として比叡山での 20 年の修行を重ね、そのはてに苦悩の中で山を下り、東山吉水教団に法然上人をたずねられます。親鸞聖人 29 歳、法然上人 69 歳でした。「ほとけの願いは、どうにもならない私達のような人間を救うために発された教えである。ただ、南無阿弥陀仏を称えることによってのみ、すべての人は救われる」との法然上人の教えは親鸞はもちろん、大衆の中にさながら海原の潮の様に波及して行きます。
法然上人との出遭いから 6 年後、朝廷より念佛停止命令が下ります。法然上人は土佐に、親鸞聖人は越後(新潟県)に、僧の身分を奪われ罪人として流されます。
京都で生まれ育った聖人にとって越後での生活は心身ともに骨身にしみたことと思われます。
しかし、その逆縁を縁として、土に生きる名もなき人々と共に、「非僧非俗」「愚禿」と名告り、ともなる人々を御同朋、御同行と敬いつつ、90 年の生涯を、ひとりの念佛者としての道を歩み続けられたのです。
2011 年、宗祖親鸞聖人 750 回ご遠忌が 5 年後に勤められますが、それと同時に、いなそれ以上に法難の意味を現代社会の有り様の中にしっかりと位置付け、時代の潮流に惑わされることのない確固たる人生でありたいと念ずるものです。
大自然につつまれて
責任役員 赤間 栄夫
今年の干支は、十二支の第 11 番目に位する戌であり、戌は酉から北へ 30 度の方角です。昔の時刻の名で、今の午後 8 時頃またはおよそ午後 7 時から 9 時の間の時刻です。かくいう私は戌年生れですが老犬です。この世の中で絶対と言い切ることは難しいことですが、誰れもが絶対死ぬまで生きることができます。ただし死がはやいかおそいかは、だれもわかりません。
- ▼私達の正しい宗派の名称
- 宗祖親鸞聖人の著「教行信証」に「真実之教・浄土真宗」と表しておりますが、本願寺はもと「大谷」という場所にあったので大谷派と言ったのでしょう。東本願寺派と言った方が世間には分かり易いでしょうが、法規上正確には「真宗大谷派」という名称です。
- ▼仏様への合掌礼拝
- 私達は仏様に合掌礼拝をしますが、合掌礼拝をしたからといってみな正しい信心の人でしょうか。形の上での合掌礼拝がすべて真宗の信心の人であるというわけではないと思います。
「お金が儲かるように」「病気が治るように」「家内安全商売繁昌」とか、自分の思いどおりに都合よくことがはこぶようにしてくれというわけでしょうが、これは人間の自分勝手な願いです。
私達人間は必ず対価の要求あるいは交換条件をつけます。しかし、大自然は決してそんなことはありません。たとえば、太陽・空気・水などこの中のどれか一つでもなければ人間は生きてゆくことができません。でも大自然は人間に対して、対価や交換条件など何ひとつ求めておりません。しかも人間は自力ではどうすることもできない大自然の無条件のただ中に生かされているのです。人間は人間の考えを基盤にした世界に沈み込みその中での人間の考えを真実と思っております。したがって誠の真実にめぐりあうことは不可能ではないでしょうか。私達を救おうとしている阿弥陀仏の本願を聞くことが、私達の人生の最も大切な課題だと思います。弥陀の本願を聞くこの内なる深い心が身の上に形となってあらわれ合掌礼拝し仏のみ名を称えることが誠の合掌礼拝ではないかと思います。 - ▼同一市民
- いよいよ来たる 3 月 31 日には 1 市 6 町の古川市・鳴子町・岩出山町・松山町・三本木町・鹿島台町及び田尻町が合併し、人口が約 14 万人という県下で第 3 の市「大崎市」が誕生いたします。各市や町では 1 月中旬から下旬にかけて、それまで協議の整った「大崎市の事務組織機構」や「住民自治活動組織のあり方」、「各種行政サービスの住民負担」等の内容について、住民説明懇談会が開催され合併に対する幅広い意見や提言を聞いておったようです。
合併まではそれぞれ古川市・岩出山町・鳴子町に居住しており、浄土真宗という同一の宗門十派(本願寺派・大谷派・高田派・佛光寺派・興正派・木辺派・出雲路派・誠照寺派・三門徒派・山元派)の中の大谷派という同じ宗派の一員としてのつながりのおつきあいでしたが、合併をしますと、大崎市という同一の市の同じ住民であるというもうひとつの深いつながりができ、より一層の親交が生れるのではないでしょうか。
浄泉寺では寺報(倶会一處)と護寺会報を年にそれぞれ 1 回づつ発行しております。門信徒の皆様が常々思っていること、お気付きになられたことなど是非ご寄稿下さいますようよろしくお願い申し上げます。
町という名のつく イベントとまたひとつ 越えて迫りぬ新市大崎
赤間有涯 詠む
境内スケッチ 成願寺
組報「親鸞の風」スタッフ
阿部 章真
大雪を降らした日本海の寒波が奥羽山脈を越えて古川の街を凍らせる。県北の中心に位置する古川市は、新幹線の駅もあり県北の要所的存在である。
そんな街の中にいても自然に生かされているのだと、冷風は私に教えてくれていた。
訪れた成願寺は、古川の中心部にあり、周りには市役所、市立病院、警察署などが点在している。
そんな中にひっそりと真新しい本堂が寒さをこらえる様に建っていた。堂内でストーブを焚き、温かく迎えてくれたのは、赤羽根證信浄泉寺住職と坊守さんだった。現在この成願寺の代務住職として兼任されている赤羽根氏は、隣町岩出山から見えたのに、「遠い所ご苦労様」と笑顔で私を受け入れてくれたことに、外の寒さが吹き飛ぶ感じがした。赤羽根氏と成願寺は古くから関係があった。
明治 11 年、当時 4 ヶ所程あった近隣の法座を現在の地にまとめられたのは、現住職の祖父圓界氏である。
畑だったこの地を、松谷林兵衛氏より譲り受け、二間ほどの民家を移築し、成願寺の前身となる古川説教所とされた。
赤羽根氏は「この地に浄土真宗が根付く基盤となったのは、やはり慶念坊の存在だったのではないか」と私に話してくれた。
年月が過ぎ、明治から大正、昭和と時代を経た昭和 29 年、この古川説教所を「成願寺」として以来約 50 年の時を経た今、墓地整備され、老朽化した本堂も五年ほど前に建て替えられた。
ご門徒の方々の思いは熱いものがあり、別院の報恩講にはバスをチャーターして団参、明治から続いている二十八日講には、皆で本堂を清掃し、持ち寄ったものを分け合って食べられているらしい。「来て良かったと言われる楽しいお寺にしたい、それが集える場になることだし、その集いが続いて行くことこそ大切ななのではないか、それには、目や耳はもちろんだが一番は口でしょう(笑)」と。
明治維新以後発展したこの街は、他所からの移住者が多く、今お講に集う半数の方はその人々であるという。そんな街の変遷と共に成願寺もまた、説教所から寺院へと歩み続けてきた。
「今は、ご門徒さんと本音で話し合えるようになって来たところです。そういう意味では、お寺としての基礎を作っている時だと思う。立派な柱や、素晴らしい屋根ではなく、揺らぐことのない土台になりたい」と想いを語られた赤羽根氏の言葉には、これまでの様子やこれからの姿を見据えたものがあるのだろう。
寒さ厳しい冬空の下、説教所に歩いて向う人々と、颯爽と自転車に乗ってお寺に集う人々が重なって目に浮かぶ古川の午後だった。
仙台組推進協主催 23 回 聞法会
於浄泉寺
弥陀の本願を信じ、念佛申せばほとけとなる、良く耳にする言葉であります。
さて、この言葉を、私達は素直に「はい、わかりました」と受け入れられているでしょうか。
10 月 8 日、仙台組内各寺から、毎年参加されている方やはじめて出席された人達で、浄泉寺はいっぱいになりました。
23 回を重ねたこの集いを主催する組推進協の役員さんは幾度か集まり準備をされて、手際良く会を進行され、この会の主題である講話は会場の住職の担当という約束のもと、午前 11 時から、講題は「しんじんのうた」テキスト、勤行本(赤本)を用いての講義としました。
正信讃は同朋会運動を推進して行くため、正信念佛偈を現代語にわかりやすくより身近なものとする為に用いられているものですが仲々使用する機会もないと思っておりました、それをあらためて声を出して読み、うたうことで、お互の音を聞きながら、内容をたしかめ合うという手法をとりました、正信讃はほとんどの人が、はじめての経験だったが、皆一生懸命、声を出し、時間の経つのが、早く感じられました。
昼食は、これまでの仕出し弁当ではなく、浄泉寺流、お土産付、特製カレーライスで空腹を満し、寺は心の安らぎと交流の場であることを実践し、全員で「如来大悲の恩徳は、身を粉にしても報ずべし、師主知識の恩徳も、ほねをくだきても謝すべし」の、声たからかに明年の会への再会を誓い散会いたしました。
東北別院報恩講と日光方面への旅
住職
東北別院講恩講に団参するようになって、今回で 5 年になります。
10 月 16 日午前 10 時の勤行に参詣の後、ご法話を聴聞して昼食をいただき、午後 2 時、貸切バスで栃木県まで行くことにしました。「日光を見ずして、結構ということはない」と、たとえ話でいわれる日光鬼怒川温泉への旅は、いつものことながら、はずむ様な気持を乗せ、少年少女時代の修学旅行気分にひたることが出来、あの頃の思い出話が、誰れ彼れとなく続き、バスの中は、若い熱気で笑いのたえない 3 時間。
ホテルにつき、ゆったり温泉につかり、夕食は、うた、おどりなどで座が盛り上がり、寺での語らいと又ちがった雰囲気の中でお互の親交を深められました。
翌日の日光は邪魔にならないほどの小雨模様で、久しぶりの東照宮詣りでしたが、今日は年に一度のすばらしい千人神輿行列とのこと、大祭に偶然出会えて本当にラッキーなひとときでした。無事の上に、予定になかったさらなる豊かな満足とともに、足どりも軽やかに帰宅いたしました。
年回表(平成 18 年)
| 一周忌 | 平成 17 年 | 三回忌 | 平成 16 年 | 七回忌 | 平成 12 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十三回忌 | 平成 6 年 | 十七回忌 | 平成 2 年 | 二十三回忌 | 昭和 59 年 |
| 二十七回忌 | 昭和 55 年 | 三十三回忌 | 昭和 49 年 | 三十七回忌 | 昭和 45 年 |
| 五十回忌 | 昭和 32 年 | 百回忌 | 明治 41 年 |
あとがき
昨年 12 月、50 年来の親友の死に立ち合った。12 月 17 日夜病院のベットで私に手をのばし、何かを話そうとする彼に、あとのことは心配するな、しっかりと生きることへの意志は強く持て!と励ました。しかし、19 日朝 8 時 69 年の生涯をとじた。
2 年前亡った奥さんとともに角膜を提供、医学に少しでも役立つならと、解剖まで約束していたという。経済的には決して裕福でなかった両親も又アイバンクへの登録者だった。
その両親の生き方が彼の人生の礎となっていたのだろう。
生死の苦海ほとりなし ひさしく沈める われらをば 弥陀弘誓の船のみぞ のせて必ず わたしける
この和讃がとても好きだと、茶をすすりながら、朴訥に話す彼の笑顔とともに、さびしい年の暮れであった。
(住職記)
宝池山浄泉寺 宮城県玉造郡岩出山町字浦小路113