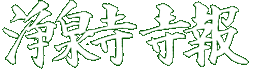
◆平成 21 年 1 月 20 日(第 14 号)
発行者 浄泉寺住職 赤羽根 證信
御同朋の輪 広がれ
浄泉寺住職 赤羽根 證信
一一のはなの なかよりは 三十六百千億の 光明てらして ほがらかに いたらぬところは さらになし(浄土和讃)
新しい平成21年を迎え、門信徒の皆様と共に慶賀に思うことでございます。
私にとりまして生を受けて以来6目の丑年となり馬齢を重ねてはおりますが、今日まで生きて来られましたのは皆様のお陰様と存じあらためて感謝申し上げます。おそらくは最後の干支になるだろうと思っております。
昨年4月に洛京し、本山春の法要に組長として最後の参詣をさせていただきました。
6月14日に発生した内陸地震での被害は幸い人命にはおよばなく、本堂、庫裡などの建物は最少の被害でした。ただ墓石のそれは甚大で未だ整備されずに残されておるところもございます。当時は早速に本山、教区、組内の多くの方々からお見舞いや激励を賜りました。御同朋の厚い思いに感謝の念ひとしおでございます。
翌6月15日かねてから予定しておりました宗祖親鸞聖人七百五十回ご遠忌お待ち受け上山奉仕にご門徒6名で詣らせていただきました。併せて帰敬式を受式いただき、得がたいご縁を賜って参りました。その後11月3日本廟ご正忌報恩講に向けての帰敬式に2名の方が参加されました。このことは、真宗同朋会運動の一貫として位置づけられており継続して参りたいと思っております。
また、毎月10日に開催しております正信偈の集いが2年目を迎えた6月より感話のリレーを行っております。文字通り参加者一人ひとり日頃感じていることを短い時間にお話しをする、そのことによって、お互いがここに集い座しているそれぞれの思いが伝わって来て非常に嬉しい限りです。
本年はいよいよ宗祖親鸞聖人七百五十回ご遠忌を間近に控えて、お待ち受けの行事、さらには仙台教区主催事業である親鸞教室が1月から1年間古川成願寺を会場に開かれることになっており、すでに内容等も決まり進めて参っております。
また、6月上旬には仙台組の事業として上山奉仕が行われます。その折にも帰敬式を併せて行って参ります。ご縁がございましたら是非ご参加いただきます。
本来寺は聞法の道場であり、私達が生涯学習をする場として皆様の心の拠りどころになる様精進して参りたいと念じております。何卒よろしくお願い申し上げます。
合 掌
法然と親鸞
責任役員 赤間 栄夫
- ▼法然
- 法然は法然房源空といい1133年(長和2年)美作国(岡山県)久米郡の押領使の子として生まれ、幼名を勢至丸といい9歳のとき、父時国は所領のことで明石定明の恨みをかい、夜襲にあって殺されてしまいました。いまわの際に時国は勢至丸を枕元に呼んで、「もし、お前が成長して仇を討つならば、相手の子がまたお前を仇として討つであろう。そうなれば、お前の子がまた相手を仇として討たなければならなくなる。仇が仇をよんで際限がなくなるから、お前は私の仇を討たずに敵を憎まず、敵も味方も共に救われて行く道を歩んで欲しい」と遺言して亡くなりました。
- ▼亡き父の意志を継ぐ
- 勢至丸は父の遺言通りに出家して、13歳で比叡山に登り、西塔の北谷源光に師事、次いで東塔功徳院の皇円に師事して天台の学問を学び、奥儀を極めたといわれます。彼は一生涯に一切経(釈迦一代の教説)を5回読んだといわれる程の大秀才で「智恵第一の法然房」と称される学識を兼ねそなえる僧でした。しかし、俗化した当時の比叡山の有り方に絶望した彼は、18歳のとき黒谷(現在の京都市右京区)に隠遁し、慈眼房叡空に師事、このとき法然房源空と名のったといわれております。
- ▼浄土念仏
- 浄土念仏(煩悩のけがれを離れた清らかな世界を求めて念ずること)を求めるようになったのは法然房源空と名のった頃からなそうです。法然以前にも比叡山や南都・高野山等でも浄土念仏が実践されておりましたが、それはあくまでも諸行(念仏以外の多くの行)の中の一つとして修められていました。法然は求道を重ねましたが真の安心立命を得ることが出来ず煩悩を重ねる中で、43歳のとき、唐の善導大師の「観経疏」(観無量経の注釈書)の中の一節「としごろ習いたる智恵は、往生のためには要にも立つべからず」に出会い、今まで習っていた智恵は、往生のためには何の役にも立たないと自覚して専修念仏に帰したといわれております。念仏には称名念仏(口に阿弥陀仏の名号を唱え心に念仏すること)と、観想念仏(端座し、思いを正して想いをこらし、一人の仏の相好の功徳荘厳を念ずること)がありますが、法然が称名念仏一行の実践のみを選択し、他の諸行の必要性を認めなかったということは、仏教が初めて庶民一般のものとして開放されることになった画期的な意味をもっています。
- ▼吉水にて草庵を営む
- 1198年(建久9年)に、ときの関白九条兼実の要請にて「選択本願念仏集」略して「選択集」を著しております。 法然は東山吉水に草庵を営み、人々に専修念仏を勧め始めるや「一天四海の人々皆専修念仏に帰し、都は称名念仏の声、巷にあふれる」という状態であり、親鸞が法然の門をたたいたのも、まさにこのような状況の時でした。
- ▼親鸞、法然の弟子となる
- 親鸞が法然の弟子となったころには、法然のもとに弁長、幸西、隆寛、証空、長西、源智など有力な弟子が数多くいましたが、その中で新参者でありながらも親鸞ははやばや頭角を現わし、法然の著作「選択集」の書写を許され、題名の字と「南無阿弥陀仏往生の業は念仏を本となす」の字、それらに綽空(親鸞)の署名を法然が書いたと親鸞自身が「教行信証」の後序で明らかにしております。 法然は特別な高弟にのみ書写を許したといわれておりますので親鸞は法然の弟子の中でも、すでに有力な一人であったことが窺われます。
(親鸞の教えに学ぶ)
浄泉寺からご案内
- 親鸞教室に参加してみませんか
- 毎月一回、成願寺を会場に親鸞教室を開催します。
開催の願い 「真宗門徒の証をたてる」
真宗大谷派では昭和37年から「真宗同朋会運動」を展開してまいりました。これは私たち一人ひとりが親鸞聖人の教えに依って生活する「真宗門徒」になって行こうとする純粋な信仰運動です。その運動の更なる広がりと深まりを願いこのたび親鸞教室を開催いたします。
私達は日常の生活の中で実に様々なことがらに出会っています。辛いこと、悲しいこと、嫌なこと、楽しいこと等々。楽しいことばかりなら心の中も落ち着いていられますが、一寸した出来事で怒ったり悲しんだりといった繰り返しの日々ではないでしょうか。私達の悩み、苦しみとは一体何なのでしょう、もちろん人それぞれ違いますし、解決の方法もあるでしょう。その時何が正しくて何が間違いなのかを判断する「ものさし」は何でしょうか。本当に拠りどころとなる人生の「ものさし」とは、この教室では親鸞聖人の教えに触れ、自分自身を見つめ直し、共に話し合うことを通して、人生の本当の拠りどころを見つけることを願いとしています。皆さんのご参加をお待ちしています。
会場 古川 成願寺 開催日 一月から毎月一回
講師 常盤俊成師 (花巻組 安祥寺)
申込み・問い合せ 浄泉寺(72-1168)
主催 真宗大谷派 仙台教区教化委員会
報恩講巌修
浄土真宗にとって一年で最も重要な仏事である報恩講は、それぞれの寺の事情により実施されております。
- ▼成願寺報恩講
- 古川成願寺は11月第3日曜日に門徒会総会を兼ねて行っていますのでほとんどのご門徒さんが詣られます。 午前9時30分より総会、10時30分参加者全員で正信偈と念仏、和讃、回向、お文があがり、仙台教区教導張崎寛裕師によるご法話をいただき、参加者全員が一堂に会してお斎をいただきながらの懇親と懇談、そして住職から一人ひとり全員の紹介があり、和気あいあいのうちに、一年間の反省と新しい年度の行事などを話し合い、さらなる協調を誓い合いました。
- ▼浄泉寺報恩講
- 11月23日浄泉寺恒例の報恩講が厳修されました。毎年開かれる行事でも、その日を迎えるための準備には相当な時間を要するものです。 当日はいつもの様な好天に恵まれ午前9時30分副住職の調声によるみんなでおつとめ、正信偈同朋奉讃式を唱和、10時から組内ご寺院ご住職様方の助音により住職の導師で正信偈真四句目下、念仏、和讃の後、ご法話がありました。 今年から仙台日辺徳照寺住職佐藤和丸師により講題「五つの不思議」はじめてお話しをいただきましたが、個性あふれる話術と絵による手法に、聴講された方々から「時を忘れる様なすばらしい講話でした」との話しをいただきました。 鬼首のご門徒の皆さん、古川のご門徒の皆さんには、それぞれバスでの団体参拝を賜りました。 年を重ねるごとに充実した報恩講になりましたことを、担当当番講ならびに役員一同心より感謝申し上げます。
真宗の仏事「帰敬式」について
帰敬式を受式することは、仏・法・僧の三宝に帰依する生活を明らかにし、仏弟子としての人生を歩んでいただきたい、このことを願いとしております。
その三宝とは、まず第1に仏を宝とする、仏に遇うということが宝となる。第2に法、仏法を宝とする。第3に僧宝、仏の教えを大切にし、その教えによって生み出された人々との出遇いを宝とする。この3つの宝を敬う身にならせていただくという意味で帰敬式を受け、一人ひとりが新しい名前、法名を名のるわけです。
そして、この三宝に帰依することは、仏弟子としての生活をはじめる上での基本となる誓いでありますが、その帰依のこころを表したものが「三帰依文」です。
その冒頭の
人身受け難し、いますでに受く。 仏法聞き難し、いますでに聞く。 この身今生において度せずんば、 さらにいずれの生においてかこの身を度せん。 大衆もろともに至心に三宝に帰依し奉るべし。
という言葉をたしかめておきたいと思います。 私たちはいかなる者としてこの身を生きるのか、いったいどういう身として三宝に帰依するのか、そのことをあらためて問いたずねる様な言葉ではないでしょうか。考えて見ますと、私とはこの身の他にないわけですが、なかなかこの我が身をそのまま受け止められないのが日ごろの私達です。 「人身受け難し、いますでに受く」、まずこの身に受けているいのちをいただき直すというところからしか私の歩みは始まらない。と三宝に帰依するという誓いがもつ意味を重ねて問いかけられているのです。
(同朋新聞より)
年回表(平成 21 年)
| 一周忌 | 平成 20 年 | 三回忌 | 平成 19 年 | 七回忌 | 平成 15 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十三回忌 | 平成 9 年 | 十七回忌 | 平成 5 年 | 二十三回忌 | 昭和 62 年 |
| 二十七回忌 | 昭和 58 年 | 三十三回忌 | 昭和 52 年 | 三十七回忌 | 昭和 48 年 |
| 五十回忌 | 昭和 35 年 | 百回忌 | 明治 44 年 |
コラム「正信偈の集い」

平成19年7月から始まった「正信偈の集い」が毎月10日の朝6時30分から行われています。
最初の参加者は10数人程度でしたが徐々に増え続け、現在は20人前後になりました。
一部の方を除いて殆どが始めての方でしたが、今では声も良く出て堂々としていて、全員で唱和する正信偈は素晴らしいものです。
皆さんも是非参加してみてはいかがでしょう。
あとがき
寺報第14号が何とか1月中に発行でき、今、ほっとしているところです。
平成8年に「寺報」「会報」の発行を始めて以来、門信徒皆様と寺とのコミュニケーションツールとしての役割を果たしてきたものなので、編集には特に気を遣って参りました。
また、コミュニケーション作りの手段としては、もう一つ「研修旅行」があります。毎年東北別院の報恩講に参詣した後、1泊で行う近隣地域への旅行と、2年に1度「本山参詣」に併せた2泊の旅行が行われております。
いずれの事業も寺と皆様との架け橋となるものですので皆様の積極的な参加を期待しております。
「寺報」「会報」への寄稿と研修旅行への参加について改めてお願いいたします。
大坂
宝池山浄泉寺 宮城県大崎市岩出山字浦小路113