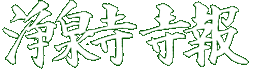
◆平成 23 年 1 月 20 日(第 16 号)
発行者 浄泉寺住職 赤羽根 證信
宗祖親鸞聖人750回ご遠忌法要を縁として
浄泉寺住職 赤羽根 證信
新年 あけましておめでとう
ございます
2011年(平成23年)いよいよ、宗祖親鸞聖人750回ご遠忌法要の年を迎えました。
「今、いのちがあなたを生きている」(ご遠忌テーマ)、今あらためて宗祖としての親鸞聖人に出遇うとはどの様な思いなのか、そして、出遇うという自分自身の生活はどの様なものか……。
振り返れば、50年前、昭和36年、宗祖親鸞聖人700回ご遠忌に本山(京都東本願寺)でご遠忌スタッフとしてご奉仕申し上げ、全国各地から参詣されるご門徒皆さんを受け入れるお世話をさせていただくご縁をいただきました。
ご遠忌は50年毎、つまり生涯に一度との思いがあり、懸命にご奉仕できた充実感が、今の私を支えているのだと思うのです。以来50年、幸いなことに健康に恵まれ、様々な条件をも克服出来、生涯2度目のご遠忌に遇わせていただくとは何ということだろうと感得するばかりです。
昨年4月本山で浄泉寺住職任命以来50年の表彰を受けましたことも、ご門徒皆様のご教示ご支援の賜物と思っております。
また、宗祖親鸞聖人750回ご遠忌お待ち受けと古川成願寺本堂建設10周年の節目として、かねてより念願いたしておりました劇団希望舞台の「釈迦内柩唄」の公演が盛会に実施できましたことも、私の生涯の思い出に残る特筆すべき事柄でありました。
「私達は生涯をかけて唯一人のひとに遇うために生きている……それは私自身である」との先達の言葉があります。
宗祖としての親鸞聖人に遇うとは、私の生涯を丸ごと信じ、願っている……「念仏申す身を生きよ」との如来の呼び声に答えることだと思っています。
現代は無縁社会と表され個人主義の主張・風潮が謳歌される中にあって、ともに生きること、つながりを生きることの大切さを教えている仏教思想、浄土真宗の「日々念佛して弥陀にたすけまいらすべし」の精神を共に生き伝える生活があらためて確かめられるのです。
1人で生きる時は2人と思え、その1人は如来からの呼び声であると宗祖親鸞聖人は私達を励ましてくれています。
今年4月25日には本山参詣の計画を別紙にてご案内しておりますので、この機会に是非お詣りいたしましょう。
何卒本年も宜しくお願い申し上げます。
合 掌
承元の法難 法然と親鸞の別離
責任役員 赤間 栄夫
- ▼安楽房と住蓮房とのスキャンダル
- 安楽と住蓮が東山鹿ヶ谷(現在の法然院)で別時念仏会を催した時、宮廷の女官である松虫・鈴虫が参加して外泊をしたという事件が起きました。それにはいろいろな説があり、女官がその場で出家をして尼になったとか、あるいは安楽達が女官を呼び礼讃にまぎれ灯火を消して不思議なことがあったとか、女官達が安楽達を呼び寄せて夜の間とどめたなど、いずれにせよ真相ははっきりしませんが、念仏停止の勅が下されました。
首謀者の安楽・住蓮のうち、安楽は京都六条の川原で、住蓮は近江の国(滋賀県)の真渕で斬首されました。ちなみに女官松虫・鈴虫が出家したといわれる法然院の南側に安養寺という尼寺が建立されています。 - ▼法然・親鸞の配流
- 後鳥羽上皇は法然を四国の土佐に、また門弟のうち行空・幸西・親鸞等は越後国(新潟県)に流罪になりましたが、なぜ親鸞が流罪になったかについては、はっきりしていません。しかしいろいろな説があり、親鸞は京都にいたころすでに妻帯していたのではないか?それが流罪の原因ではないだろうか、あるいは法然より「選択集」の書写を許されていて、門下のうちでも高弟であったからとか、ある説では親鸞の思想が一念義に近くきわめてラジカルで、朝廷からは特に危険思想として睨まれていたからではないかなど、いずれの説も推測の域を出ていませんが法然の門下の中でも高足としての存在であったことは間違いないと思います。
- ▼念仏停止の命
- 法然は四国の土佐に流罪となりましたが、これは九条兼実の所領が土佐にあったことに関連しているようです。法然上人には自分の所領である土佐に逗留してほしいという兼実の配慮も働いていたと思われます。事実、兼実は承元元年2月に念仏停止の命が下された同年の4月に法然流罪を心痛しながら世を去っております。
しかし、法然が土佐にまで赴いた形跡はなく、讃岐国まで赴いたのち、赦免になるまで留まり、地頭や村人、漁夫や遊女に至るまで教えを説いたと伝えられています。
「承元の法難」と称されるこの事件について、ときの朝廷は本心から専修念仏を弾圧したいと願っていたのではなく、南都北嶺側の圧力を何とか持ちこたえていたところ、安楽・住蓮の不祥事が発生しついにおさえきれなくなったというのが真相だったようです。
流罪に赴く法然の思い
この思いを法然は「四十八巻伝」に次の様に書き遺しております。
流刑さらにうみとすべからず、そのゆへは齢すでに八十歳にせまりぬ。たとひ師弟おなじみやこに住すとも、娑婆の離別近きにあるべし。たとひ山海をへだつとも、浄土の再会なむぞうたがはん。(略)しかのみならず、念仏の興業洛陽(京都)にしてとしひさし、辺鄙におもむきて、田夫野人をすすめん事、季定(年来)の本意なり。しかれども時いたらずして、素意いまだはたさず、いま事の縁によりて、季来の本意をとげん事すこぶる朝恩ともいふべし。
配流をも専修念仏弘道の機縁にしようとする法然の悠々たる態度は、誠に素晴らしいものがあります。法然の最大の魅力は、彼のいささかも自己を卑下せず、しかも妥協もせず、また包容力にあふれた彼の人間性にあることがよく分ります。親鸞がなぜあれ程までに法然に私淑帰依したかもよく理解出来るところです。 親鸞は法然と反対方向の新潟に配流され、二人の師弟は別れたまま、この世で互いに再会することはありませんでした。
(親鸞の教えに学ぶ)
釈迦内柩唄を観て (投稿)
庄 司 悦 子
去る9月2日、古川パレットおおさきで公演された、水上勉作「釈迦内柩唄」という劇を観た。
演題を見たとき、以前読んだ作品同様、作者自らの生い立ちを重ね合わせたような暗く、重く、どろどろとしたものを想像した。
しかし、有馬理恵さんが演じる主人公「薮内ふじ子」には、焼き場の人間ということだけで人間性まで否定され、疎まれ蔑視される世界に生きながらも、父親が守り通してきた運命の仕事を受け継ぎ、けなげに生きようとしている姿には暗さはない。水上文学の別の一面を見た思いだった。
小さな扉のむこうに赤々と燃える世界。人はそこで生身の体から灰へと化してゆく。死ねば誰でもが行かなければならない世界。
そして、その扉の中へと送り込む人。それが焼き場の人間。父親が、酒の手助けを借りながら、やり続けた仕事。誰かがしなければならない仕事である。
死んで、送り込まれた扉のむこうの世界には、身分の違いや貧富の差はない。死んで焼かれ、灰になればどんな人でも同じように野に撒かれ、美しい花を咲かせる。
主人公「薮内ふじ子」は、その花々に父親の分け隔てのないやさしい心を感じた。
有馬理恵さんは、主人公が焼き場の人間として、父親の仕事を引き継いでゆこうと決断するまでの心の有様を、明るく、ユーモラスに演じ、観客を笑わせてくれる場面もあった。
幕が下りたとき、満席の観客から大きな拍手が送られた。
久々にすばらしい演劇を観て、会場に入ったときの思いとは逆に、大きなバック絵の秋空に咲き乱れるコスモスのように、爽やかな気持ちになっていた。
年回表(平成 23 年)
| 一周忌 | 平成 22 年 | 三回忌 | 平成 21 年 | 七回忌 | 平成 17 年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十三回忌 | 平成 11 年 | 十七回忌 | 平成 7 年 | 二十三回忌 | 平成元年 昭和 64 年 |
| 二十七回忌 | 昭和 60 年 | 三十三回忌 | 昭和 54 年 | 三十七回忌 | 昭和 50 年 |
| 五十回忌 | 昭和 37 年 | 百回忌 | 大正 2 年 |
平成22年報恩講
報恩講は、浄土真宗の寺院では重要な行事で、宗祖親鸞聖人のご命日(11月28日)を縁として「親鸞上人の教えに遇う」法座です。
浄泉寺報恩講は、毎年11月23日(祝日)と実施日が定着していることもあって、今年も大勢の方々のご参詣をいただき盛大に行われました。
午前9時30分、副住職の調声による「みんなでお勤め」に始り、「責任役員挨拶」があり、続いて午前10時に「ご満座勤行」が執り行われました。
ご満座勤行には組内のご住職が参集され、その助音と住職の導師で厳粛かつ盛大な勤行となりました。
午前11時にはご法話「お笑ひ絵とき説法人生の根本問題」を、仙台市徳照寺住職佐藤和丸師よりいただきました。
師のご法話は一昨年から3度目で、門徒の皆さんも良くご存じのため初めからノリが良く、師ご自身の体験や象に触れる盲人たちの例を挙げた下りには、涙を拭きながら笑っている門徒さんも居たほどで、その軽妙な説法(語り口)に聞き入っておりました。
「今年が最後です。」と師は何度もおっしゃいましたが、またお聞きしたいと思った方は数多くおられたのではないかと思います。
その後、担当(二ノ構・本町・仲町)の皆さんが用意されたお斎をいただき散会いたしました。
ご参詣いただいた門徒の皆さんは100名以上にも達し、その中には、古川や鬼首から態々バスでおいでになった方々も居られました。
また、報恩講前に行う「おみがき」は、昨年まで何日も要していたのですが、皆さんの応援もあり一日で終わることができました。
役員、地区担当の方々、ご門徒の皆様に支えられて無事報恩講を実施できましたこと、心から深く感謝申し上げます。
年増考
いつもの「朝の集い」で「若年増」という言葉が飛び出した。
知らないという人もいて、話の輪が広がった。
今では死語に近い言葉だと感じたが「年増」とは、「娘盛りをすぎて、やや年をとった婦人。江戸時代には20歳過ぎをいい、今は、普通には30歳代の婦人にいう。」とある(広辞苑)。
しからば、若年増は25歳頃までで以降は中年増、30代を過ぎると大年増というのか……
江戸時代には10歳から15歳で結婚したことで、こんな風に定着したのだろう。
現代の平均寿命は80歳を超え超高齢化社会になった。そんな中結婚もできずにいる大年増があたり前になり、結婚だけが女の幸せではないなどとぬかす。さながら、それは化石年増とでも表そうか…
あとがき
浄泉寺成願寺に係る記念となる事が重なったのをご縁に「釈迦内柩唄という舞台公演を開催したい、古川で会場下見をする」という連絡がご住職から入った。
それで、当日会場候補地に出向いたら、そこには劇団希望の代表と舞台製作の方、成願寺の方数名が居られ、下見を終え食事会場に行くと、「スタッフはここに居る皆さんで進めます」ということで計画は実施に決まった。(いや、決まっていた?)
その後二度の実行委員会を開き、開催に向けて、チケット売り捌き、業務分担を決め、準備を進めた。
開催してみれば、会場は満席(入場者380名)。内容も素晴らしく会場は感激の渦に巻き込まれた。
この事業に関わりを持って感じたのは「門徒さんの寺に対する大きな思い」である。
特に成願寺の皆さんに感謝感謝!!
大坂
宝池山浄泉寺 宮城県大崎市岩出山字浦小路113